今回は独立・起業関連の話をしたいと思います。
勤めている会社のセカンドキャリア制度を利用して、4月から休職。そして、6か月経過しました。
早期退職を決めてから休職までのこと、休職してからこの6か月でしてきたことを紹介したいと思います。
・40才以上で独立・起業を考えている人
・独立・起業の準備中の人
・独立・起業に興味がある人
この記事を読めば、早期退職後の過ごし方がわかります。
セカンドキャリア制度(早期退職)とは、次の仕事を始めるための準備期間として最大1年間休暇がとれる制度です。休暇中は、休職前と同額の給与が支給、厚生年金や健康保険も休職前と同様の扱いです。
早期退職を募集する際、退職金の割り増し支給などありますが、次の職場が決まっている、すぐに事業がスタートアップできる人向けだと思います。
給与をもらいながら、厚生年金や健康保険も休職前と同様の扱いで、次のことを考え、行動できるセカンドキャリア制度は、非常にありがたいものです。
早期退職を決めてから休職までのこと
ほとんどの会社の定年は60歳、定年退職するか、嘱託で65歳まで雇用延長。
それが一般的な日本のサラリーマンの王道だと思います。
早期退職を選ぶ道とは…

早期退職を決めた理由
IT業界は建設業界とよく似ています。
SIベンダーの多くは、一次請け(元請け)でプロジェクト管理、実際の構築や開発は二次受け、三次請け(下請け、孫請け)ですることがほとんどです。
規模が大きくなるほど、その傾向が高いと思います。
会社で一定の年齢になり管理職になると、半期ごとに予算を与えられるわけですが、予算を達成するには多くのプロジェクト、規模の大きいプロジェクトをこなす必要があります。
業務内容もプロジェクト管理(進捗・原価・品質の管理)が主流になり、実際の構築や開発からどんどん遠ざかってしまいます。
このまま自分のやりたいことから遠ざかる、それが最大の理由だったと思います。
早期退職の報告
私が勤めていた会社では、半期毎に業績面談というものがあります。
管理職のセカンドキャリア制度解禁が50歳でしたので、2年前ぐらいに、セカンドキャリア制度を受けたいと上司に伝えました。
早期退職することがわかると、職場での役割も徐々に裏方にシフトしていきました。
休職開始までの半年
仕事の引継ぎを早めに計画化して、後任に負担を掛けないように引継ぎをしていきました。
早期退職の会社への申請は3か月前でした。
このころから、起業関連の調査と休職後の過ごし方を計画化していきました。
今、振り返って思うこと
もし、ブログやアフェリエイトでの収益を考えているのであれば、休職の最低1年前ぐらいから、サイトを立てて、準備しておくべきだと思います。
余程の運がないかぎり、収益がではじめるまで1年以上かかると思います。
記事の内容も大事ですが、サイトが検索にひっかることがないので、見向きもされません。
フリーランスで個別に仕事を受けることを考えているのであれば、在職中に、自分の売り込みとお客様に恩を売っておくとよいと思います。
自分の市場価値を知るのに転職もひとつの手段です。

休職してからこの6か月でしてきたこと
休職前に計画を立てておくと、いざ休職に入っても迷うことがありません。

起業なのか、フリーランスなのか
税務署に開業届を提出し、事業することを起業とするならば、目指すところは起業です。
個人で仕事を請け負う働き方をフリーランスとするならば、フリーランスのエンジニアとして、仕事を請け負う働き方もします。
休職して直ぐにしたことは、フリーランスのエンジニアとしての登録です。
どんな仕事があって、どれぐらいの報酬なのか情報が収集できます。
契約書周りの対応や営業活動はせずエンジニアリングに集中したい方にオススメです。

アプリケーション開発の目指すべき分野
4月と5月はアプリケーション開発の目指すべき分野を決めるために、調査しました。
プラットフォーム関連で、AWS(AmazonWebService)とGCP(GoogleCloudPlatform)のユーザ登録、無料で使用できる範囲で、各サービスの特性を調査しました。
開発言語、ソフトウェア関連でオープンソースを中心に、どの程度使用できるか、ダウンロード、試験的なコーディングで、評価しました。
アプリケーション開発で収益を考える場合、スマホのアプリ開発が最適と考えています。
理由は、GooglePLAYやAppStoreで開発したものを公開、収益を確保する仕組みが整っているからです。
収益を確保する方法としては、アプリに価格を設定して有料アプリとする方法、広告収益として無料アプリとする方法、無料アプリとして利用するなかで課金する方法があります。
GooglePLAYやAppStoreでアプリを公開するには、デベロッパー登録が必要です。
デベロッパー登録には費用が発生し、AppStore(iOSアプリ)の場合、毎年11,800円(税別)必要です。
GooglePLAYの場合は登録時の25$だけです。GooglePLAY(Androidアプリ)の方が圧倒的に低コストです。
私は自分が使っているスマホがAndroidであったこと、また開発用PCがWindowsであったことから、GooglePLAY(Androidアプリ)を選択しました。
アプリを公開する場合、プライバシーポリシーの公開が必要なため、サイトが必要になります。
サイト
6月は自分のサイトをもつために、ドメインを取得、レンタルサーバを契約、サイトを構築しました。
お名前.comでドメインを取得、レンタルサーバはConoHa WINGを契約しました。

このサイトを構築するときに検討したことをまとめました。
これからサイトを作る方は、是非♪
ドメインを取得するなら、ココです♪

初めて自分のサイトを持つなら、ココです♪
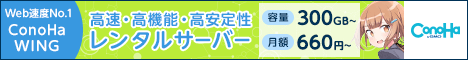
価格重視でサイトを持つなら、ココです♪

サイト構築後は、最初にアプリ公開で必要なプライバシーポリシーの公開、プロフィールを公開しました。
次にサイトで収益をあげるための広告、アフェリエイト関連でASPと契約しました。
ASPとの契約自体は無料ですので、可能なかぎり多くのASPと契約したほうがよいでしょう。
契約しているASP様をご紹介♪
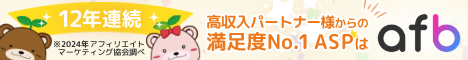
ポートフォリオ
サイト構築と合わせて、クリエイターとして自己紹介用のアプリ開発に着手しました。
アプリ公開までの期限を3か月として、Androidアプリを開発しました。

GPS走行記録アプリ Archive
ジムカーナなどのモータスポーツ向けのGPSを利用した走行データの記録やセッティング情報を記録するアプリです。
GPSタイム計測アプリ Laps
GPSの位置情報を利用して、事前に登録したゴール地点(2点間)を通過するまでの経過時間を計測するアプリです。
加速度・傾き計測アプリ Sensor
内蔵センサーを利用して、加速度と傾きをグラフ表示するアプリです。
モニタリング
アプリ公開後から10月にかけては、サイトにアフェリエイト記事の投稿、公開したアプリのモニタリングを行いました。
モニタリングとは、サイトやアプリの利用者の反応をみながら、手を入れていくことです。
サイトへの誘導として、SNSの利用やアナリティクスで分析しました。
アプリについては、機能追加や有料アプリを開発しました。
今、振り返って思うこと
起業する場合、最初にすべきことは、自分のサイトをもつことだと思います。
それも、できるだけ早く、在職中に済ませて、サイトである程度収益が見込める状態(または、検索でサイトが上位に表示されるなど浸透している)までしておくほうが、精神的によいと思います。
サイトのコンテンツ拡充ももちろん重要ですが、余程の運がないかぎり、安定してサイトとして機能するまで、1年以上かかると考えています。
起業を決意したら、
まずは自分のサイトをもつことに着手してください。
アプリ公開もサイト同様で見つけてもらえるまで時間がかかります。
運も必要ですし、SNSを利用した売り込みも必要です。
日本のスマホのシェアは、6割がiPhoneなどのiOS、残りの4割がAndroidです。
Androidの場合は、海外も視野に入れたほうがよいでしょう。
日本だけで考えるならiOSがよいでしょう。
開発フレームワーク(エンジン)として、FlutterやUnityを使えば、iOSやAndroidなどを含めてクロスプラットフォームで開発できますので、両方で収益を上げたいのであれば、選択肢の一つとして考えてもよいでしょう。
これからの6か月ですること
サイトやアプリでサイトで収益をあげるための活動と、開業届の提出など開業の準備と考えています。
・開業届で必要となる屋号を決めること(実はドメインを取得するときに既に決めています)
・屋号での銀行口座の開設とクレジットカードの作成(退職前に必ずすませること)
・青色申告(開業届の提出にあわせて)
・小規模企業共済の加入
・確定申告
・国民年金加入
・健康保険(国民健康保険か任意継続健康保険のいずれか選択)
今回はここまでです。
誤字脱字、意味不明でわかりづらい、
もっと詳しく知りたいなどのご意見は、
このページの最後にあるコメントか、
こちらから、お願いいたします♪
ポチッとして頂けると、
次のコンテンツを作成する励みになります♪
参考になったら、💛をポッチとしてね♪
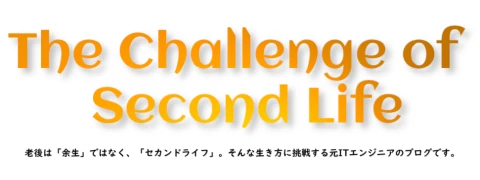







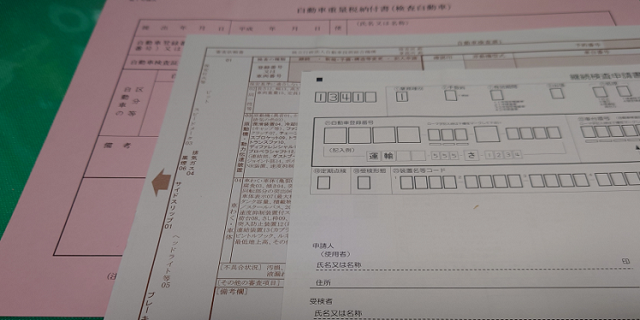
コメント欄